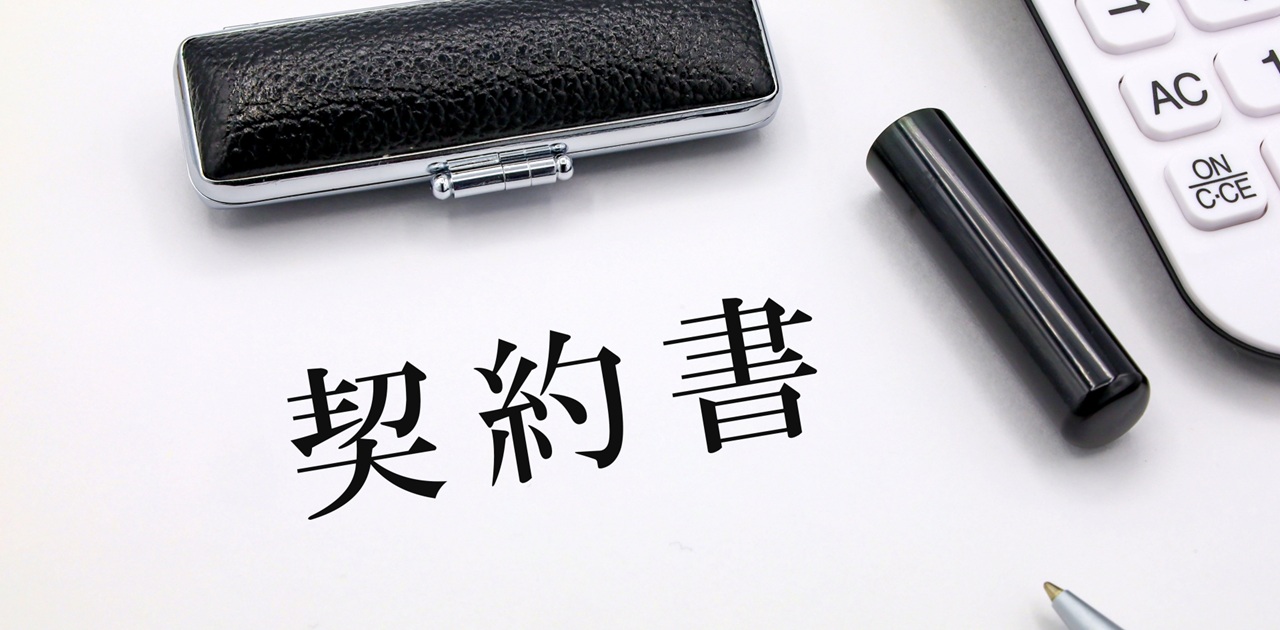不動産を売却するときに結ぶ「媒介契約」には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。その中でも専任媒介契約は、不動産会社1社に販売活動を任せる契約形態です。
「営業力を集中してもらえる一方で、本当にこれでいいの?」と不安になる方も多いでしょう。
本記事では、専任媒介契約の意味や他の契約との違い、売主・仲介業者双方のメリットとデメリット、契約前の注意点、向いている人の特徴まで徹底解説します。
 豊川
豊川契約前にぜひ参考にしてください。
専任媒介契約とは
不動産を売却するときには、複数の契約形態から仲介方法を選ぶ必要があります。その中でも専任媒介契約は、売主と1社の不動産会社が独占的に契約を結び、集中的に販売活動を行う方法です。
ここでは、まず専任媒介契約の定義や、一般媒介契約・専属専任媒介契約との違いを整理します。
専任媒介契約の定義
専任媒介契約は、不動産の売却を特定の不動産会社1社だけに依頼する契約形態です。
契約期間は宅地建物取引業法で最長3か月と定められており、期間中は他の業者に依頼することはできません。また、契約から7日以内に不動産流通標準情報システム(レインズ)へ登録し、2週間に1回以上の販売状況報告を行う義務があります。



業者にとっては販売活動に集中でき、売主にとっては進捗を定期的に把握できる点が特徴です。
一般媒介契約との違い
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。
競争が生まれ、販路が広がるメリットがありますが、各社の営業活動が分散し、熱意や広告投下量が低くなる場合もあります。一方、専任媒介契約は1社に絞るため、営業リソースが集中し、戦略の一貫性が保ちやすい特徴があります。
また、専任媒介ではレインズ登録や定期報告が義務付けられていますが、一般媒介はこれらが任意で、情報管理や進捗把握の面で差があります。


専任専属媒介契約との違い
専任専属媒介契約は、専任媒介契約と同様に1社にのみ売却を依頼する契約ですが、大きな違いは「自己発見取引」の可否です。
専任媒介契約では売主が自ら買主を見つけた場合、直接契約できますが、専任専属媒介契約では必ず仲介業者を通さなければなりません。また、レインズ登録期限は5日以内、販売状況報告は1週間に1回以上と、専任媒介よりも短いサイクルで義務が課されます。管理体制が厳格になる分、業者のサポート密度が高まる契約形態です。
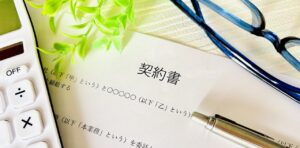
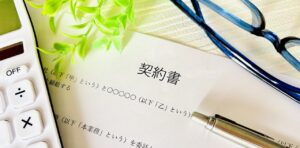
| 観点 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専任専属媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 契約できる業者数 | 複数業者と契約可能 | 1社のみ | 1社のみ |
| 売主の自己発見取引 | 可能 | 可能 | 不可 |
| 業者の販売努力 | 分散されやすい | 集中してもらえる | より強力に販売活動してもらえる |
| レインズ登録義務 | 任意 | 7日以内に登録義務 | 5日以内に登録義務 |
| 業者からの活動報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約期間 | 最長3か月 | 最長3か月 | 最長3か月 |
専任媒介契約の売主にとってのメリット


専任媒介契約は、売主にとっても多くの利点があります。特定の1社に依頼することで営業力を集中させ、販売戦略の一貫性や情報管理のしやすさが向上します。
ここでは、売主視点での具体的なメリットを3つのポイントに分けて解説します。
優先的に扱ってくれる
専任媒介契約では、不動産会社はその物件を他社と競合せずに取り扱えるため、営業リソースを集中して販売活動を行いやすくなります。
広告費や時間を優先的に投入してもらえる可能性が高く、ポータルサイトでの上位表示やチラシ配布、現地販売会など積極的な販促を受けられるケースもあります。売主としては「他社に先を越される心配がない」という業者側の心理を利用でき、担当者のモチベーションも高まりやすくなります。
定期的な販売状況報告がある
専任媒介契約では、宅地建物取引業法により、2週間に1回以上の販売状況報告が義務付けられています。これにより、広告反応や内覧件数、購入希望者の反応など、売却の進捗を定期的に把握できます。
情報が集約されるため、売主は現状を冷静に分析でき、戦略の見直しや価格調整の判断もしやすくなります。一般媒介契約ではこの報告義務がないため、専任媒介契約ならではの安心感と管理のしやすさが得られます。
価格調整や戦略変更がスムーズ
1社との専任契約なので、売却価格の見直しや広告方針の変更などをスピーディーに行えます。
複数社と契約している場合は、全社に連絡・調整する必要がありますが、専任媒介契約では窓口が一本化されているため意思決定が速く、情報の行き違いも防げます。
また、買主からの条件交渉も一本化されるため、柔軟かつ効率的な対応が可能です。結果として、売却スピードや成約条件の最適化につながりやすいのが特徴です。
専任媒介契約の仲介業者にとってのメリット
この契約形態は、仲介業者側にも大きな魅力があります。競合を避けつつ販売活動を進められるため、広告投資や営業計画を積極的に行いやすくなります。
ここでは、業者視点のメリットを整理し、その背景にある業界の実情も交えて解説します。
成約の独占権がある
専任媒介契約では、売主が他の不動産会社に同時依頼できないため、成約すれば必ずその業者が仲介手数料を得られます。営業活動を行っても他社に横取りされるリスクがないため、業者側は安心して広告費や人員を投入できます。
また、独占的に取り扱える物件は自社の営業戦略上も重要で、顧客への紹介や販売計画を長期的かつ積極的に展開しやすくなります。



この「独占権」が業者の販売意欲を高める大きな要因です。
営業戦略が立てやすい
1社のみで販売を担当するため、広告の出稿計画や内覧のスケジュール、販売期間に応じた戦略の立案がしやすくなります。一般媒介契約のように「他社が先に成約してしまい広告費が無駄になる」というリスクが低く、長期的な販売計画にも踏み切りやすいです。
また、販売活動の内容を細かくコントロールできるため、物件の魅せ方や販促ツールの作成も一貫性を保てます。こうした計画性は、成約率の向上にもつながります。
両手仲介を取りやすい
専任媒介契約では、売主からの依頼が1社に限定されているため、自社で買主を見つけやすくなります。これにより、売主と買主の双方から仲介手数料を得られる「両手仲介」の可能性が高まります。
もちろん宅建業法では囲い込み行為は禁止されていますが、実務上、自社顧客とのマッチングを優先する動きは珍しくありません。業者にとっては利益率を高められるメリットであり、販売活動の強化にもつながるポイントです。
専任媒介契約のデメリット
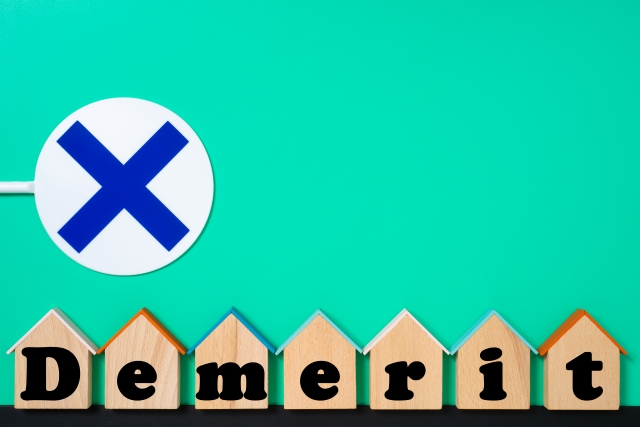
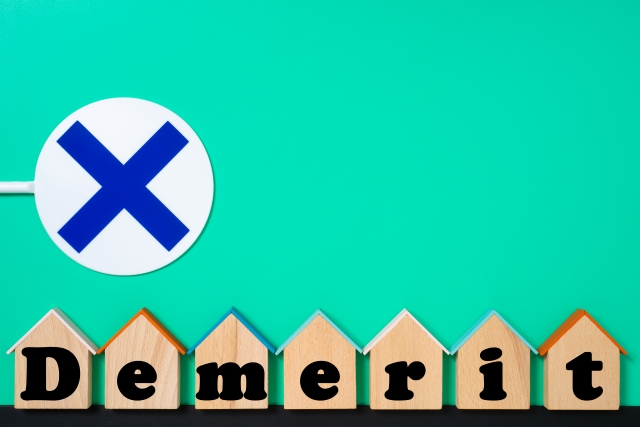
メリットが多い一方で、専任媒介契約には注意点やリスクも存在します。営業活動の停滞や囲い込みの可能性、契約期間中の柔軟性の低下など、売主が知っておくべきポイントがあります。
ここでは3つのデメリットに分けて解説します。
販売活動の停滞リスクがある
専任媒介契約は1社独占のため、担当者の優先順位が下がった場合や物件が売れにくいと判断された場合、広告や内覧の対応が消極的になる可能性があります。
複数社が競合する一般媒介契約と違い、他社に取られる危機感が薄れることで、販売スピードが落ちることもあります。契約上は販売活動の義務がありますが、実際には熱量の差が売却結果に直結するため、契約前に担当者のやる気や実績を確認することが重要です。
両手仲介による買主制限の可能性がある
専任媒介契約では、自社で買主を見つけられる「両手仲介」の機会が増えるため、業者が他社からの買主紹介を積極的に受けない可能性があります。
これは宅建業法上は禁止されている囲い込み行為ですが、現場では起こり得る問題です。その結果、買主候補の幅が狭まり、売却スピードや価格面で不利になることもあります。
契約前に販売活動の透明性や、他社との連携方針を確認しておくことがリスク回避につながります。
契約期間中の変更が難しい
専任媒介契約の有効期間は最長3か月で、その間は原則として他社へ依頼することはできません。契約を途中で解除して乗り換えることも可能ですが、業者によっては広告費や活動費の精算が必要になる場合があります。
担当者との相性が悪かったり、販売戦略に不満があっても、すぐに切り替えられない点はデメリットです。契約前には販売計画や方針を具体的にすり合わせておくことが重要です。
専任媒介契約を結ぶ前に確認すべきポイント
契約形態の選択は、不動産売却の成否を左右する重要な判断です。特に専任媒介契約では、業者選びや条件設定が結果に直結します。
ここでは、契約前に必ず確認しておきたい3つのチェックポイントを紹介します。
業者の販売実績と得意エリア
契約前には、その不動産会社がどの程度の販売実績を持っているか、特に物件所在地周辺での取引経験が豊富かを確認することが重要です。
得意エリアに強い業者は、地域の相場や購入希望者層を熟知しており、適切な価格設定や販促が可能です。
また、ポータルサイトやチラシ、現地販売会などの実績事例を見せてもらうと、販売力のイメージが掴めます。過去の成約事例や平均販売期間など、数字での裏付けもチェックしましょう
担当者との相性・信頼感
専任媒介契約は最長3か月間、1社の担当者と密にやり取りするため、相性や信頼関係は成否を左右します。
説明が分かりやすいか、レスポンスが早いか、質問への回答が具体的かなどを事前に確認しましょう。
また、売却戦略や価格提案が根拠あるものか、売主の希望や状況をしっかり聞き取ってくれるかも重要です。契約前の面談ややり取りで、誠実さやコミュニケーションの質を見極めることが重要です。
契約期間と更新条件
専任媒介契約の有効期間は最長3か月で、更新には再度の書面契約が必要です。
契約時には、期間満了後の更新条件や、途中解約の可否・方法を確認しておくことが大切です。また、契約期間中の販売戦略(値下げタイミングや広告手法の変更時期)も事前にすり合わせておくと安心です。
条件が不明確なまま契約すると、思うように売却が進まなかった場合に柔軟な対応ができない可能性があるため、慎重に確認しましょう。
専任媒介契約が向いている人
すべての売主に専任媒介契約が適しているわけではありません。売却の目的や状況によって向き不向きがあります。
ここでは、この契約が特に効果的に機能する売主の特徴を具体的に紹介します。
信頼できる不動産会社・担当者を見つけている人
すでに実績や評判から「この会社・担当者なら安心して任せられる」と確信できる場合、専任媒介契約は効果的です。
1社に任せることで営業活動が集中し、広告・内覧対応・価格戦略などが一貫して進められます。特に過去の取引経験や知人からの紹介で信頼できる担当者がいる場合、無駄な競合を避けて効率的に売却を進められます。
契約前に担当者の熱意や販売計画を確認し、相互理解ができていれば成功確率は高まります。
売却活動にあまり時間を割けない人
仕事や家庭の事情などで売却活動に多くの時間を取れない人には、専任媒介契約が向いています。
1社とのやり取りだけで済むため、複数業者との連絡・調整の手間が省けます。また、販売状況の報告義務(2週間に1回以上)があるため、忙しくても進捗が把握しやすく、状況に応じた判断も可能です。
遠方からの売却や投資物件の処分など、現地に頻繁に足を運べない場合にも有効な契約形態です。
売却期間にある程度の余裕がある人
専任媒介契約は契約期間中に他社へ依頼できないため、短期間で必ず売却しなければならない状況には不向きです。
一方、売却時期に余裕がある人なら、1社とじっくり戦略を練りながら進められるメリットがあります。時間をかけることで、適切な買主を見つけやすく、条件交渉にも余裕を持てます。
相場や市場動向を見ながら価格調整を行いたい人には、特に向いている契約形態です。
専任媒介契約に関する良くある質問
最後に、契約に関して売主が抱きやすい疑問や誤解を解消します。仲介手数料や契約期間、レインズ登録など、よくある質問をQ&A形式でまとめました。



契約判断の参考にしてください。
まとめ
- 媒介契約には「一般媒介、専任媒介、専属専任媒介」の3種類がある
- 専任媒介契約は1社に依頼し、営業リソースが集中するのが特徴
- 売主のメリットは「優先的に扱ってもらえる、定期的な販売報告、戦略変更がスムーズ」
- デメリットは「販売活動が停滞するリスク、囲い込みの可能性、契約期間中の柔軟性低下」
- 契約前に確認すべきは「業者の実績・得意エリア、担当者との相性、契約期間と更新条件」
- 向いているのは「信頼できる業者がいる人、売却に時間を割けない人、売却時期に余裕がある人」
専任媒介契約は売主にとっては「優先的に扱ってもらえる」「進捗を把握しやすい」といった利点があり、業者にとっても「成約の独占権」「営業戦略が立てやすい」といったメリットがあります。ただし、活動が停滞するリスクや囲い込みの懸念もあるため注意が必要です。



契約する際は、それぞれのメリット、デメリットをよく理解して慎重に行いましょう。